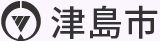ページID:873041164
津島市食品安全委員会
最終更新日:2025年9月11日
津島市食品安全委員会とは
目的
食生活に関連する分野での安全性を増進し、市民の現在と将来にわたる安全な食生活を確保することを目的として設置されています。
委員会名簿(令和7年9月2日現在)
| 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|
| 委員長 | 猪飼 誉友 |
中部大学 生命健康科学部 非常勤講師 |
| 副委員長 | 宇藤 久子 | 津島市女性の会 |
| 委員 | 尾関 聡 |
津島保健所環境・食品安全課長 |
| 委員 | 石黒 光宏 |
海部農林水産事務所農政課長 |
| 委員 | 鬼頭 陽子 |
一宮生活協同組合 |
委員 |
成田 直美 |
一宮生活協同組合 |
委員 |
日下 京子 |
津島・愛西母親連絡会 |
委員 |
平光 佐知子 |
コープあいち |
委員 |
垣見 圭子 |
津島市健康づくり食生活改善推進協議会 |
委員 |
大島 幸枝 | 津島市市民くらしの講座実行委員会 |
食品安全委員会報告
直近の報告は以下のとおりです。
令和7年度テーマ「食料自給の現状」
議題 「食料自給の現状」
猪飼委員長より「食料自給の現状」をテーマに、パワーポイントを使って、食料自給の低下がもたらす影響と今後の展望について情報提供がされた。
1 情報提供の内容
・日本の食力自給率は約37%。
・1492年のコロンブスがアメリカ大陸を発見し、人が流入したことで、耕作が始まった。
・産業革命も相まって食料生産が増加。それに追随する形で人口も増加。
・2050年頃には人口は1.3倍になる見込み。それに対して、食料需要は1.7倍。特に、畜産物需要が増える見込み。畜産物には、穀物も必要とするため穀物の需要も大きくなっていく。
・畜産物1キログラムを生産するために必要な飼料量は、牛肉が最もコストパフォーマンスが低い。(11キログラムのトウモロコシが必要)
・食料は外交戦略物資としての側面を持つ。すなわち、自国の食料の自給体制を整えることは、国策の一つでもある。他国に依存しすぎると、奪い合いが生まれ、最悪のケースでは紛争にも発展する。
・バイオエタノールやバイオディーゼルにも原料として農作物が利用されている。特に、トウモロコシが利用されている。
・輸出国が特定の国に限られるため、国際価格が大きく変動しやすく、現在では、世界の食料価格は史上最高を記録している。
・現在、地球上には90億人分以上の穀物が生産されているが、多くの穀物が家畜の飼料に回されていることや食品ロスが発生しているため、世界人口の約80億人を養うことができない。
・先進国においては、必要以上にカロリー摂取をしている。
・食料の輸入重量に輸送距離を乗じた数値をフード・マイレージと言い、日本は世界一の数値となっている。
・食料自給率にはカロリーベースと生産額ベースがある。日本はカロリーベースで計算するのが一般的。アメリカやヨーロッパは生産額ベース。
・日本の食料自給率の低迷の原因として、地政学的な事情、労働賃金の高騰、生産・輸送・保存技術の向上、生活水準の向上が挙げられる。
・諸外国と比較すると、日本の国土の三分の二は農耕に適さない山林であるため、労働集約型の工業に頼る他に選択肢はなかった。
・輸入生産物を日本で賄うためには、国土面積の三分の一の面積が必要となる。
・食料供給への不安があると答えた人のうち、8割が「国内生産による食料供給能力が低下するおそれがあるため」と回答している。
・国は食料自給力指標としておおよそ一人あたり1日2000キロカロリー必要としている。米・小麦・大豆中心で作物を生産すると、必要カロリー数には届かない。いも類中心であれば供給可能。
・国は、緊急事態食料安全保障指針を作成し、平時と緊急時の取り組みを公表している。また、「フード・アクションニッポン」等の啓発運動も実施している。
2 各委員からの意見、意見交換
・全国有数の農業県である愛知県の食料自給率が低い理由は、生産物の中に花が含まれていることが理由の一つとして挙げられる。
・自給率に関連して、愛知県民の野菜の摂取率の低下が目立つ。