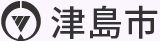ページID:873504539
不妊・不育
最終更新日:2023年12月15日
不妊・不育専門相談と経済的支援
愛知県は以下の事業をおこなっております。
愛知県の不妊・不育相談
愛知県では、名大医学部附属病院に委託して、専門医師やカウンセラーなどの専門家による「不妊」「不育」についての相談窓口を設けています。
「流産、死産後の不安」「特別養子縁組制度でお子さんを育てたいと考えている」などの相談にも対応しております。
詳しくは愛知県不妊・不育専門相談センターホームページをご覧ください。![]() 愛知県不妊・不育専門相談センターホームページ(外部サイト)
愛知県不妊・不育専門相談センターホームページ(外部サイト)
愛知県の不妊症・不育症ピアサポート活動
愛知県では、公益社団法人愛知県助産師会に委託して、愛知県在住の妊活動中・不妊治療中の方、流産・死産・生まれて間もないお子様を亡くされたなどの経験をされたご家族に対して、当事者同士が互いに語り合うことによる支えあいや、寄り添いの場を提供しています。
詳しくは公益社団法人愛知県助産師会不妊症・不育症ピアサポート活動事業ホームページをご覧ください。![]() 公益社団法人愛知県助産師会不妊症・不育症ピアサポート活動事業(外部サイト)
公益社団法人愛知県助産師会不妊症・不育症ピアサポート活動事業(外部サイト)
愛知県の不育症検査費助成事業
愛知県では、不育症検査に対する助成をおこなっています。
詳しくは愛知県のホームページをご覧ください。![]() 愛知県ホームページ・不育症検査費助成事業(外部サイト)
愛知県ホームページ・不育症検査費助成事業(外部サイト)
愛知県の特定不妊治療費助成事業
愛知県の特定不妊治療費助成事業は令和4年4月より不妊治療が保険適用されたことに伴い、令和4年度をもって終了しました。
詳しくは愛知県のホームページをご覧ください。
一般不妊治療助成事業
津島市の一般不妊治療助成事業は、令和4年4月より不妊治療が保険適用されたことに伴い、令和4年度をもって終了しました。